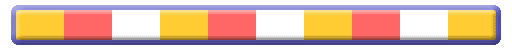
|
谷口 浩美選手(旭化成) 「谷口さんにとって自分らしさって何ですか。」 マラソン選手として有名な旭化成の谷口さんのお話が終わった後の最初の質問だった。 「普通、ランナーは、自分のために走ります。僕も、ある出来事が起きるまでは、そうでした。でも、今の僕は違います。僕は、僕が走ることによって喜んでくれる人が、いる限り、走り続けます。」既に、何度も引退が取り沙汰されていた1998年の夏、その当時、37歳だった谷口さんが、NEC女子バレー部の合宿所で熱く語ってくれた。 ちょうど10年前、ソウル・オリンピックの代表選考会をかねた、福岡国際マラソン。駅伝の名門、旭化成のランナー達は、充実していた。誰が走っても代表選手になるだけの力を持っていた。テレビ局は、何ヶ月も前から取材を続けていた。1位から3位までの代表枠を旭化成の軍団が独占するのではないかとの噂にも、疑問を持つ者はいなかった。当然、谷口選手も、最高の仕上がりで、自分でも怖いくらいに絶好調だったと言う。 しかし、計算できなかったのは、その日の気温。雲行きは見る見るうちに妖しくなり、気温は下がり、ついに雨を通り越して、雹(ひょう)まで降り始めた。暖かい宮崎県の延岡を本拠地に練習をしている旭化成軍団にとって、予想もしなかった誤算である。 谷口選手も、その天候の中、苦しんだ。筋肉はこわばり、足が思うように前に出ない。寒さに対して、心も体も準備できていなかった。必死で前を追うが、気ばかりが焦り、どうしようもなくなったときに覚悟を決めた。「とにかくこのまま走りつづけよう。そして、化成の誰かに抜かれたら、彼に全てを託してやめよう。」すさまじいまでの愛社精神。しかし、旭化成の他の選手たちも寒さにあえいでいた。ついに誰にも抜かれないまま、ゴールに入る。4位。旭化成からの代表選手なし。完敗であった。ショックではあったが、誰も責められないと、その時は思ったそうだ。 本当の衝撃は、何日も経ってからだった。追跡取材をしていたテレビ局が、ドキュメンタリー・タッチで番組を作った。そこに映し出された自分たちの姿。そして、谷口選手に戦慄が走る。それは、映像に映し出された宗兄弟を見た瞬間だった。実際に走った誰よりも、スタッフとして裏方に徹していた宗兄弟が、一番悲しそうだったと言う。 「なんてこと、してしまったんだ。」その時、事の重大さに気付いた。これまで自分達と共に苦しみ、時には指導者として、時には兄貴として、いつも側にいてくれた一番大事な人達に、こんな思いをさせてしまった。「二人に笑顔を取り戻すことが出来るのは、俺だけだ。」そこから、谷口選手の本当の戦いが、始まった。 3年後、東京で開催された陸上の世界選手権、日本人による金メダルがひとつもないまま迎えた最終日、男子マラソンは、行われた。3年がかりで準備し、緻密な計算の上で、誰もが嫌うラストの「心臓破りの坂」に勝負をかけた。そこまでは、誰が前に出ても忍耐あるのみ。先行逃げ切り型の選手も、ラストスパートが得意な選手もいる。谷口選手は、自分自身でどちらのタイプでもないと言う。「しいて言えば、武器がないことが特徴ですね。」と謙遜する谷口選手は、色紙に「忍耐」と書く。そうだ。彼の武器は、耐え忍ぶこと。忍耐そのもの。 陸上関係者は、旭化成の長距離軍団を「強い」と表現する。エリート集団ではないかもしれない。しかし、毎日、練(ね)られている彼らは、相手に強さを感じさせる。長距離の選手たちでありながら、背中に「気合い」を感じるのだ。一緒に走るライバルに、「とてもかなわない」と思わせる迫力。 この日の谷口選手は、「雑草のごとく」走ったのではなかった。3年前の失敗から、自分が記録を残したレース、勝ったレースの徹底分析をした。気温が比較的高い中で、好調であることを最初に指摘したテレビ局にも、協力を依頼した。秋口とは言え、まだ気温が高い9月に行われた世界選手権をリベンジの舞台に選んだのも、理由があったのだ。水分補給も研究した。脱水になりやすい条件下での、高速レースを想定して実験を続け、細胞の一つ一つを水分で満たす方法を考えた。レース前の3ヶ月間は、イメージしていた通りの食事、睡眠、そしてもちろん練習をこなした。 快挙は、周到な準備と緻密な計算に、限りないまでリアルなイメージの上に成し遂げられたのである。 トップで競技場に走り込んだとき、観客席の大観衆とテレビの前の我々は、日本人の快挙に歓喜した。谷口選手は、更に加速する。ゴール地点で待つ、二人の恩師のために。彼らに笑顔を取り戻すために。ゴールテープより先の二人の笑顔こそが、谷口選手のゴールだったから。 初めて人のために走った。「これまで支えてくれた旭化成の社長、陸上部の部長、靴を作ってくれたメーカーの人、そして監督とコーチに感謝します。」本音で彼はそう言った。走る前からイメージしていた通りに。 しかし、ドラマはまだ終わってはいなかった。総合閉会式までに時間があり、宗コーチと共に一旦、ホテルに帰るために暗い選手通用門から外に出た。 不意に駆け寄ってきた初老の女性に「谷口さん、本当に感動をありがとう。」と言われた。それは、あの有名な円谷幸吉さんのお姉さんだった。東京オリンピックで銅メダルを取ったものの国立競技場に入ってからのデッドヒートに敗れたこと、次のオリンピックへの国民の異常なまでの期待が重圧になったっこと、恩師と離れ離れになり孤立した事、何が本当の原因だったのか我々に知る由もないが、お世話になったすべての人に感謝の言葉を書き綴った遺書を残して自らの命を絶った円谷さんのお姉さん。「いつか誰かが、弟、幸吉の果たせなかった夢を実現してくれる日本人が…。」その思いで、その日も国立競技場へ足を運んだ。 27年の時を経て、谷口選手は、知らないうちに誰かの夢を現実にした。心の一番深いところから喜んでくれる人のために。「僕が走ることによって喜んでくれる人がいる限り走り続けます。」笑顔でそう言った谷口選手には、後光が射しているようだった。 |